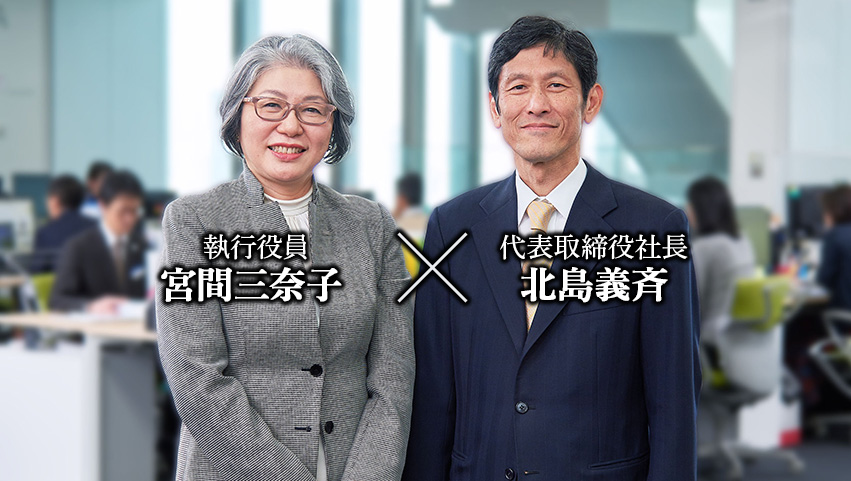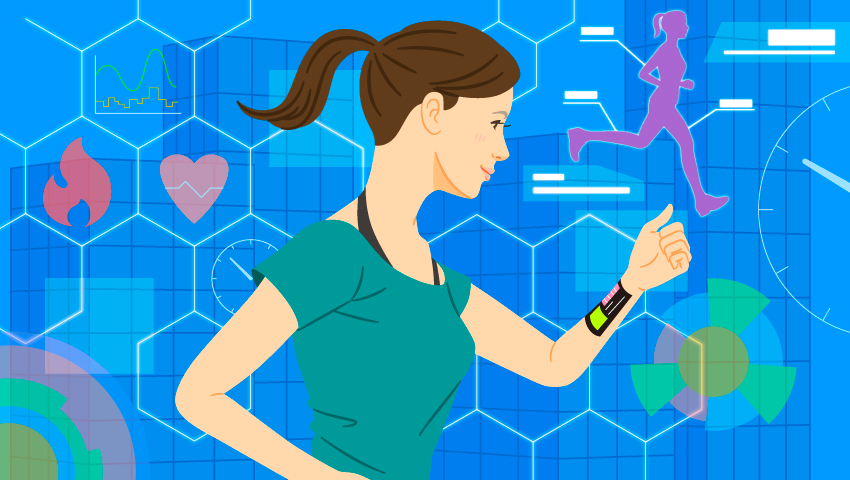CSUNカンファレンス2019を「助け合いアプリ」開発メンバーが現地レポート
- X(旧Twitter)にポスト(別ウインドウで開く)
- メール
- URLをコピー
- 印刷
「移動時に困っている人」と「手助けができる人」をスマートフォンでマッチングするサービスの立ち上げをめざす開発チームは、海外のアクセシビリティの先行事例を調査するため、2019年3月にアメリカ・アナハイムで開催された「CSUN Assistive Technology Conference 2019※1」を視察。参加したDNPの松尾佳菜子と米山剛史が会場で目にしたのは、障がいの有無に関係なく一人ひとりが能力を活かすダイバーシティが重視された社会の姿であり、そのために障がい当事者にとって必要なAT(Assistive Technology:支援技術)や、アクセシビリティに対する企業活動が発表されていたという。今回の視察で得たものについて、二人に話を聞いた。
目次
- 世界が注目する「CSUN Assistive Technology Conference 2019」
- 日本ではよく使われる「バリアフリー」を、アメリカでは何と言う?
- 人と人とのバリアをなくし、「だれもが活躍できる社会」をめざす最新製品が勢ぞろい!
- 「助けあいアプリ」が新たに開発していく、「日本独自のバリアフリー」はヒトとインフラの両輪を育てること
- ※1:「CSUN Assistive Technology Conference 2019」は、カリフォルニア州立大学ノースリッジ校が主催するアクセシビリティに関する世界最大級の学会。毎年3月に開催され、世界各国から参加者が集まる。

|
|---|
松尾 佳菜子(写真右)
大日本印刷株式会社 ABセンター コミュニケーション開発本部
「助けあいアプリ」のプロジェクト推進リーダー。サービスデザイン、リサーチ・UXデザインなどを担当。
米山 剛史(写真左)
大日本印刷株式会社 ABセンター コミュニケーション開発本部
「助けあいアプリ 」のPRなどのプロモーション全般、コミュニケーション設計を担当。
世界が注目する「CSUN Assistive Technology Conference 2019」
世界各国から5,000名を超える参加者が集まるアクセシビリティに関する大規模な国際カンファレンス、「CSUN Assistive Technology Conference 2019(以下、CSUN)」。専門家によるさまざまなセッションが開かれたほか、GoogleやAmazon、Microsoftなどの企業が開発した、最新のアシスティブテクノロジーを用いた機器やサービスが展示された。

|
|---|
| 会場では障がいのある方でも、スマホなどATを使って自力で自由に歩く姿が多く見られた |
中には、「振動の強弱によって目的地の方向がわかる視覚障がい者向けのデバイス」や「舌を使った触覚ディスプレイ」など、日本ではまだ普及していないものも数多く紹介されていた。今回初めて参加した米山は、社会的背景から多様な人が集まり、ダイバーシティについての考え方が進むアメリカと日本では、障がい者を取り巻く環境が大きく異なっていることに驚いたという。
日本ではよく使われる「バリアフリー」を、アメリカでは何と言う?
「日本では障がい者や高齢者などが社会参加するうえで支障となるバリアを取り除くことを『バリアフリー』と呼んでいますが、欧米では『アクセシビリティ』と呼びます。バリアフリーという言葉は、対象が障がいのある方に限られてしまいますが、『利用しやすさ』という意味のアクセシビリティは、対象がすべての人に広がります。
ダイバーシティを重視する社会が根付いているアメリカでは、1990年に障がいによる差別を禁止する『障害を持つアメリカ人法(ADA法)』が制定されており、障がいの有無に関係なく誰もが社会に参加できるよう、企業や学校はアクセシビリティに配慮することが義務付けられています。それによって障がい者を取り巻く環境が整備され、人々の意識も育ってきたのです」
その言葉通り、会場には車いすの方、聴覚や視覚障がいを持つ方がたくさん来場していたという。「障がいのある方一人ひとりが、自由に行動していたのが印象的でした」と米山。
|
会場には講演者の発言をテキスト表示するスクリーンが設置されている |
「会場では、障がいを持つ人が参加しやすいだけでなく、全盲・重度障がい者が登壇することを踏まえた配慮がされていました。例えば、講演(セッション)が行われる会場には、要約筆記が準備されていたり、プレゼンテーター自身で手話通訳者や点字原稿を準備して発表したり、聴講者も発言をライブテキスト化するアプリ(Google Live Transcribe)を使って聴講したりしていました。
日本で生活していると馴染みがありませんが、アメリカの企業や学校では、本人がやりたいことであれば、障がいを持つ人が支援技術を要望したり、運営者側が導入をサポートするのは普通のこと。テクノロジーを使ってコミュニケーションや行動を阻害するマイナスを解消し、障がい者のアビリティを活かして健常者と同じようにやりたいことをするという考えが浸透していました」
人と人とのバリアをなくし、「だれもが活躍できる社会」をめざす最新製品が勢ぞろい!
アシスティブテクノロジーやツールを紹介するスペースでは、ADA法のもと自治体や各企業が開発したさまざまな製品が展示され、GoogleやAmazon、Microsoft、SONYなどのブースも賑わっていました。
|
企業ブースが並ぶアシスティブテクノロジーやツールの紹介スペース |
|
舌へ信号を送る電気振動での触覚ディスプレイ |
点字を教える先生不足を解消する点字トレーニング器具 |
|
知的障害の子供とコミュニケーションをとるための指差しボード |
参加者の注目を集めたスマートディスプレイ |
米山によれば、アメリカでは製品開発の初期段階から「誰にとっても使いやすいデザイン、サービス設計をすること」が前提で、アクセシビリティという考え方がインクルードされているため、各企業で障がいを持つ人を採用し、アクセシビリティデザイナーとして活躍していることが当たり前になっているという。「障がい者」という「個性」を持った人が社会やプロジェクトに加わることで生じる「ダイバーシティ」が価値創造に結び付いているのだ。
彼らにしか気づけない、発想できないスキルを最大限に活かし、多様な人が活躍できる社会であるために、企業はさまざまな場面でアクセシビリティを踏まえたデザインをする。こうした意識が当たり前になっているからこそ、障がいの有無に関係なく幅広く社会で活躍することができるのだ。米山とともにCSUNに参加した松尾は、次のように感想を話す。
「実際に会場にいると、アシスティブテクノロジーやツールを使うことは決して特別なことではないという雰囲気を感じました。健常者も障がい者も区別なくお互いコミュニケーションを取り、“違い”を意識しすぎることはありませんでした。アメリカでは障がい者が自由に外に出て、やりたいことをして、活躍できる環境が整っているのだなと思いました。
ある講演(セッション)で『アシスティブテクノロジーを障がいのある方をサポートするだけのものではなく、すべての人に役立つユニバサールデザインに変えていかなければいけない』という話があり、障がい者が主人公の学会にもかかわらずユニバーサルデザインの発想を取り入れていることがとても印象に残っています。私たちがサービス開発をするうえでも、この視点はとても大切だと感じました」
「助けあいアプリ」が新たに開発していく、「日本独自のバリアフリー」はヒトとインフラの両輪を育てること
アメリカでは障がい者が自立して生活できるようにアクセシビリティを充実させることが一般的になっていることを肌で感じた米山と松尾。今回の視察を受けて、自らが開発するサービスを助け合いのインフラとして社会に根付かせるために必要なことが見えてきたという。松尾は、今後の展開について次のように語る。
「手助けサポートサービスのアイデアを発案し、社会実験を進めてきてからこれまで1年、障がいのある方や妊婦の方を対象にお出かけ時の困りごとを解決するサービスとして受容性の検証を行ってきました。その中で気付いたのは、移動中に困っている人は“必ずしも障がいのある人だけではない”ということです。今回のCSUNでは、障がいのあるなしに関らずあらゆる人が当たり前のように活躍できる社会の可能性を感じました。日本でも、気軽に声をかけ合うことができて、誰もがいきいきと活躍できる社会の実現をめざしていくために、私たちが開発しているサービスを誰もが使える共助のインフラとして浸透させたいと思いました。」
|
松尾の学会での思い出フォト。「障がいのある人もない人も、同じテーブルでみんなが自由にランチをしている様子。この状態こそ、共生社会を体現しているのではないか」と語る |
具体的には、当初、妊婦の方や車いすの利用者、ベビーカーユーザーに注目して進めてきたサービスを、今後は移動時に困っているあらゆる人へと対象を拡大していく予定だ。土地勘がなくて出張・旅行先で道に迷ってしまう人、スマホの地図アプリが使いこなせない人、荷物が重くて段差に困る観光客、体調が悪くて長時間立っているのがつらい人など、健常者と呼ばれる人々も状況によっては困る立場になるからだ。
「このサービスに取り組んだ背景には、世界寄付指数(world giving index)ランキングで日本は『見知らぬ人への手助け』という項目で139カ国中135位と低く、それを変えたい!という思いがありました。これまで実施した大阪や福岡での実験を通して、日本人は、そもそも困っている人の存在に気づいていないこと、気づいたとしても手助けをする際に『間違ってはいけない』と躊躇し、声がかけられていないことが分かりました。

|
|---|
困っている人からは、手を差し伸べてくれた時点で安心感を得られると聞いています。自分のできる範囲でいいので、『手助け』を行動に移せて、多様な人とのコミュニケーションを楽しめる日本人を増やしたい」と松尾は話す。
困ったときには気軽に声を上げ、困っている人に気づいたときには声をかけ、ちょっとした行動を起こせるように、人々のコミュニケーションをサポートするプラットフォームとして提供していくというのが松尾らの考えだ。
米山と松尾は目下、「助けあいアプリ」のブラッシュアップに力を注いでいる。1年かけて実証実験を進めてきて検証した要素を盛り込んで、2019年度夏頃に街なかでの手助けを促進する新たなアプリをリリースする予定だという。視覚・聴覚・肢体の障がいを持った社員を巻き込んでアプリ開発を進めているとのことで、どのようにサービスが進化するのか、楽しみに待ちたい。
- ※記載された情報は公開日現在のものです。あらかじめご了承下さい。
2019年7月にたすけあいアプリMay ii(メイアイ)として再スタート、2024年8月にサービスを終了いたしました。
- X(旧Twitter)にポスト(別ウインドウで開く)
- Linkdin
- メール
- URLをコピー
- 印刷